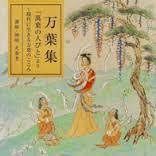- 「ひらがなの音」をしっかり発声する (参照:日本語で伝えるための技術(1))
- 「現代やまとことば」を使う (参照:日本語で伝えるための技術(2))
- きき手の「きく」活動をサポートする (参照:日本語で伝えるための技術(3))
書かれている文章を理解することと話し言葉を理解することの一番大きな違いは、いつでも前の内容を確認することができるかどうかということになります。
書かれた文章を読むという行為は、相手の関係ない読んでいる人独自の行為であり自分だけのペースで読むことが可能になります。
分かりにくい部分についてはいつでも前後の内容を参考にすることができますし、そのための時間も自分の都合でどのように使うこともできます。
そのために修飾関係が分かりにくかったり言葉同士の関係や論理が分かりにくかったりしても何度でも読み返して再確認することが可能となっています。
しかし、話し言葉では一瞬のうちに言葉が流れていき基本的には確認することができません。
せめて聞いている自分の記憶に残っている内容を振り返ることはできますが、その間にも新しい内容が伝えられていることになりますので振り返ることだけに集中することはほとんど不可能といえます。
きき方でも確認してきたように、「ひらがなの音」をすべて聞き取ることは大前提なのですがすべてを聞き取ってから理解していてたのでは次から次へと発せられる内容を理解することは難しいことになります。
そのために「ひらがなの音」を聞きながら言葉の理解や内容の理解に対しての予測が行なわれていることになります。
予測なしに「ひらがなの音」を聞き取ってからすべてを理解することは実際には不可能ではないでしょうか。
きくことの経験が増えることによって予測の精度も上がってきていることになっていると思われます。
伝える内容を定めるときに一番気を付けなければいけないことは、伝える対象者が持っている言語や言葉をできるだけ把握しておくことが必要になります。
相手の氏素性や専門分野や経歴を確認しておくことはそのためにやっていることであり、相手に対してより理解をしやすい言葉や論理を見つけるためにこそ役に立つ情報だといえます。
専門分野の違う相手に対して専門用語を多用しても理解してもらうことは難しくなるばかりになりますし、相手の理解しようとする意欲をそぐことにもつながってしまいます。
共有意思を持つことが好きな日本語感覚においては、同じ専門用語を同じように使う相手に対しては共感を持つことが多くなるものですが、反対に少し違っただけでも反感を持たれる要素にもなってしまいます。
相手の持っている言葉を確認すると同時に使ってもよい場面かどうかを確認することも大切なことになります。
特に伝える場としての環境やメンバーによっても言葉を選択する必要があります。
あらかじめ用意しておいた言葉であっても場によっては変更する必要も出てきます。
自分の言葉ではなく理解してほしい相手の言葉で伝えることが理想になります。
次は、一文をできるだけ短くする必要があります。
この場合に気を付けることは修飾語をできるだけ必要なものだけに絞り切ることが必要になります。
長文の文章の分かりにくさは多くの修飾語による修飾関係の複雑さにあります。
話し言葉で伝える内容で文章のように長い内容を伝える場合には、できるだけ細かく文章を区切ることが必要になります。
さらに、文同士の関係を明確にして相手の予測を助けるための接続詞の使い方が大切になります。
接続詞を聞いたとたんにその後に続く内容が前の文との関係において予測できるものとなるからです。
書かれた文章における接続詞の多さは全体の論理をかえって分かりにくいものとしてしまいますが、話し言葉においては一息ついて接続詞を入れることで相手の予測を利用することが可能となるのです。
最後に来るのが伝えたいことの意図です。
聞いて理解してもらうことが目的の場合は決して多くはないはずです。
それよりも理解したうえで何かをしてもらいたいことのほうが多いのではないでしょうか。
そのことをどこまで直接的に伝えるのかは場や環境によって異なると思われますが、それでも効果的な伝え方をしなければなりません。
意図が伝わらなければ「行間が読めない」という感じを味わうことにもなりかねません。
自分の意図したことと違った伝わり方をしてしまった経験は誰にもあると思います。
ほとんどの場合は「仕方ない」ということになっているのだと思います。
日本語の感覚では意図や意思をはっきりと表明することは決して効果的ではないということになります。
もちろん明確にすることが必要な場面がないわけではありませんが、実社会においては相手に応じて言葉を選び使い方を選ぶことが必要になってきます。
「ことあげ」が嫌われる日本の精神文化のなかで磨かれてきた感覚ではないでしょうか。
(参照:「言挙げ」(ことあげ)に見る日本の精神文化)
具体的な言葉としてこれらのことを自然に行なえるのが「現代やまとことば」ということになります。
(参照:「現代やまとことば」を経験する(1))
特に、相手の持っている言葉が明確になっていない場合や伝えるべき相手が明確にわかっていない場合などでは圧倒的な力を発揮する言葉となります。
専門家同士の会話においてさえもよりわかり易い言葉と使い方が尊重されているのが現状です。
一般的な人を相手とする場合には同じことを説明するのに分かりやすさが優先されるのは間違いのないことです。
自己満足的な独りよがりな表現が分かりやすさに勝ることがないのは歌においても同じことが言えます。
「現代やまとことば」による歌が歌詞の内容以上に人に伝わるのは、日本語が持っている音としての「ことだま」のチカラかもしれません。
このチカラを歌の中だけに留めておくことはないと思います。
もっと普段の話し言葉の中でも活かしていけるのではないでしょうか。
日本語が自然に持っている感覚をそのまま生かしていくことが一番伝わることになりそうですね。
・ブログの全体内容についてはこちらから確認できます。
・「現代やまとことば」勉強会メンバー募集中です。